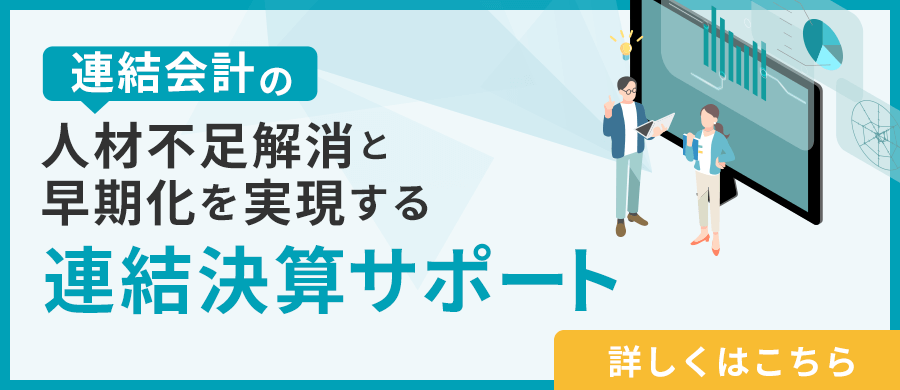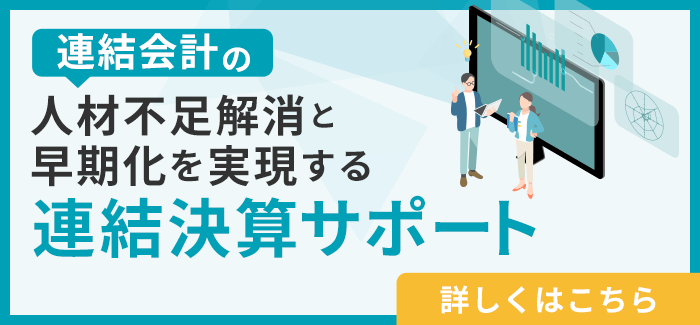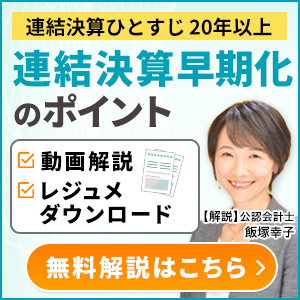非上場企業に連結決算は必要?義務・メリット・デメリットを解説

「連結決算は上場企業だけのもの」と思っていませんか?
実は近年、非上場企業や中小企業でも連結決算の導入・検討が増えています。
本記事では、非上場企業に連結決算が本当に必要か?義務の有無・メリットとデメリット・導入判断のポイントまで、わかりやすく解説。制度の基礎から実務のリアルまで押さえて、あなたの企業経営に最適な選択を見つけましょう。
非上場企業に連結決算は必要?
基本と法的義務
連結決算の義務や必要性は、非上場企業にとって「経営の見直し」や「今後の事業戦略」にも直結する重要テーマです。まずはその基礎と法的な原則を整理しましょう。
連結決算とは何か?
非上場企業に関係する場面
連結決算とは、親会社・子会社・関連会社などグループ全体の財務諸表を一つにまとめ、グループ全体の実態を把握するための会計手続きです。
上場・非上場に関係なく、「親会社として複数の子会社を持つ場合」「グループで事業を展開している場合」など、グループ経営の見える化や信頼性確保のために導入が検討されます。
非上場企業に連結決算が
義務付けられるケース
非上場企業でも、会社法や会計基準によって連結決算が義務となる場合があります。
主な義務付け例は以下の通りです。
- 親会社が「会社法上の大会社」に該当し、一定規模の子会社を持つ場合
- 会社法や金融機関からの要請がある場合
- 原則:連結の範囲や要件は会社法や企業会計基準に準拠
ただし、上場企業と比べると「公開・開示義務」は限定的なことが多いです。
連結決算が不要・
任意となるケースとその理由
一方、非上場企業であっても「すべての親会社に義務があるわけではありません」。
- グループ規模が小さい、子会社が存在しない場合
- 会社法上の「小会社」や「特定非営利活動法人」等、法律で除外されているケース
- 「連結決算 任意」として導入する企業も増加
任意の場合は経営の見える化や内部管理強化、将来的な上場準備などが動機となります。
非上場企業が連結決算を導入するメリット・デメリット
非上場企業においても連結決算を導入する動きが活発になっています。
その背景には、経営環境の変化やステークホルダーの期待に応える必要性など、さまざまな理由があります。
ここでは、メリットとデメリットの両面から、非上場企業が連結決算に取り組む意義と注意点を、実際の現場でよく起きる課題を交えながら詳しく解説します。
非上場企業が連結決算を行う
主なメリット
連結決算を取り入れることで、グループ全体の経営状況をより正確に把握できるようになります。
これにより、各子会社の財務状態やグループ間の資金の流れを一目で確認でき、経営判断のスピードと質が向上します。
また、連結ベースでの財務情報を開示することで、銀行や取引先など社外の関係者からの信頼が増し、資金調達や取引条件の面でも有利に働くことが多くなります。
さらに、グループ間取引の適正化やリスク管理の徹底につながり、不正や無駄の発見・予防にも効果的です。
将来的に上場やM&Aを見据える企業にとっては、早い段階で社内体制や業務フローを整えておくことで、将来の変化にも柔軟に対応できる強みとなります。
特に中堅・中小企業では、金融機関対応や信用力強化の目的で連結決算を導入する事例が増えています。
- グループ全体の経営状況を“見える化”できる
- 銀行や取引先など外部への信頼度アップ
- グループ間取引の適正化、リスク管理が強化できる
- 将来的な上場やM&Aに備えた社内体制づくり
非上場企業における連結決算の
デメリット・注意点
一方で、連結決算の導入には一定のハードルがあります。
まず、会計システムや専門家へのコンサルティング、人材の育成など、初期費用やランニングコストが発生します。
加えて、各社からのデータ収集や集約作業、内部取引の消去など、日常業務に比べて作業量が大きく増えるため、担当者の負担が増しやすい点も無視できません。
グループ内で会計処理や経理ルールが統一されていない場合、基準の違いによる調整作業が煩雑化し、情報共有やコミュニケーション不足が原因でミスや遅延が発生するケースも散見されます。
実務運用では、担当者の専門知識や十分な事前準備がないと、単なる作業増にとどまらず、連結財務諸表の正確性が損なわれたり、グループ全体の情報漏洩リスクが高まるおそれもあります。
- 導入コスト(システム・コンサル・人材育成など)がかかる
- 作業負担が大きく、社内リソースが不足しやすい
- グループ内データの標準化やコミュニケーションが不可欠
- 税務・会計基準の違い、内部取引消去の複雑さ
成功例・失敗例で見る
導入判断のリアル
実際に非上場企業で連結決算を導入した事例を振り返ると、グループ全体の経営課題をいち早く可視化し、早期に不採算子会社を再編することで経営効率を大きく改善したメーカーのように、目的意識を持って活用すれば経営にプラスの効果をもたらします。
また、連結ベースでの財務情報を銀行に開示したことで資金調達力が向上し、メガバンクから追加融資を受けることができた企業もあります。
反対に、導入目的があいまいなままシステム投資や担当者の作業負担だけが増えてしまい、結果的に運用コストばかりが膨らんでしまったケースもあります。
さらに、グループ会社間で情報共有が徹底できず、内部取引の消去が不十分で財務諸表に誤りが発生した事例も見られます。
このような成功・失敗の分かれ道となるのは、導入前に「なぜ連結決算が必要なのか」「どの範囲まで実施するか」「どの程度のリソースを割けるか」を明確に見極めておくことです。
自社だけでの運用が難しい場合は、早めに専門家やアウトソーシングサービスを活用することで、失敗リスクを大幅に低減し、安定した運用体制を築くことができます。
非上場企業の連結決算の手順と
実務ポイント
「実際に導入する場合はどう進めるのか?」具体的な手順や現場でよく起きるトラブル、対策を紹介します。
連結決算の対象範囲と
「どこまで」連結するか
- 原則:親会社が実質的に支配する子会社が対象(議決権50%以上等)
- 「持分法適用会社」や「関連会社」も必要に応じて範囲に含める
- グループ内のどこまでを連結対象とするか、法基準だけでなく実態も考慮
範囲設定の誤りは監査指摘や信頼性低下の要因になるため慎重な確認が必要です。
実務フロー・作成手順とポイント
- 各社の単体決算を完了
- グループ間取引や債権債務の消去
- 必要に応じた会計基準の調整や為替換算
- 連結財務諸表の作成・確認・発表
効率化のために「会計ソフト」や「アウトソーシング」を導入する企業も増加。自社の体制・知識に合わせたツールやサービス選びがポイントです。
Q&A|非上場企業と連結決算の
よくある質問
非上場でも親会社なら
連結決算が必要?
はい、原則として親会社は連結決算の義務が生じます。会社法や会計基準で定められた範囲に該当する場合は、上場・非上場を問わず対応が必要です。
子会社が複数あっても
連結決算は不要にできる?
一定要件(規模や支配力、会社法上の除外規定など)を満たせば、一部除外できる場合もありますが、原則として支配している子会社は連結対象です。
グループの将来上場を見据えて
連結決算を始めるべき?
はい。将来の上場、M&A、事業承継を見据えるなら、早期に連結決算の運用体制を整えることで、外部監査・金融機関対応にも有利です。
金融機関や取引先への開示は
どうする?
法的な開示義務は限定的ですが、融資・取引拡大の交渉や信頼構築の観点から自主的な連結財務諸表の開示がプラスに働く場合が多いです。
まとめ|非上場企業の連結決算は「目的とコスト」で判断を
非上場企業における連結決算の必要性は、「義務」「経営メリット」「コスト・リスク」のバランスで判断が重要です。
制度や実務を正しく理解し、自社に最適な運用方法を選びましょう。
導入に不安がある場合は、経験豊富な専門家やアウトソーシングの活用で、安心・効率的な運用を実現できます。